(きっと、問いかけ合う機会が足りていない)
ある企業様からの依頼をお聞きしているうち、直感的にこう感じました。新しいメンバーが急に増えたので、お互いの人間関係をよりよくしていきたい、という依頼でした。
人間関係は興味を持つことからしか深まらない
人間関係が深まるカギは、お互いに興味関心を持ってコミュニケーションをできるかどうかにあると思います。「私に興味を持ってもらっている」と感じられることは、社会性を重んじてきた人類にとってとても重要なことです。ただ一緒に時間を過ごすだけでは、人間関係は向上しません。
この企業様のケースでは、日々の忙しさに押されて、お互いへ興味を持つための余白が無くなってしまったのだろうと推測しました。その状態が続いてしまったことで、何気ない会話も始めにくい雰囲気になってしまったのではないでしょうか。
多くの人間は、話しかけるきっかけを見失うと、そのままズルズルと関係を固着させてしまう傾向が強いと思います。そう考えると、新入社員の歓迎会は、お酒の力を借り、気楽に問いかけあうことができる貴重な時間だったのかもしれませんね。コロナウィルスの影響で歓迎の催事が実施できなくなっている背景も、地味に痛手となっているように思われます。
自分に対しての「問いかけ」は、見知らぬおばちゃんがくれる飴玉に似ている気がします。最初はびっくりするけれど、後から思い出すとなんだか嬉しい。
今回の依頼では、こうした流れをワークショップの中に創り出したいと思いました。ビジネスでは、始めに名刺交換をすることが大前提となっているように、問いかけるという儀式さえ済ませてしまえば、その先には開かれた交流が待っているはずだからです。
エドガー・Hシャイン『問いかける技術 確かな人間関係と優れた組織をつくる』の表紙をめくると、
人間関係を築くのも、問題を解決するのも、物事を前進させるのも、すべては適切な質問があってこそうまくいく。
という一文が記されているように、問いかけが持つパワーは絶大です。
問いかけから遠慮のストッパーを外す
当日のワークショップでは、場に集ったメンバーへの問いかけを作成することから始めました。そうして出来上がった人数分の問いかけを投影し、インタビューを進めてもらうと、これまでなかなか話せたことがない、と言っていたのが嘘のように、どのペアも質問が尽きない様子でした。
表面だけをなぞれば、問いかけを作って、インタビューしあっただけのことです。ごく単純なワークショップ。
でもこのワークショップの本質は、お互いの心に潜む「遠慮」のストッパーを外しあう、通過儀礼の場としてデザインしたということです。だから、この組織のコミュニケーションがこれからどう変わっていくのか、とても楽しみなんですよね。
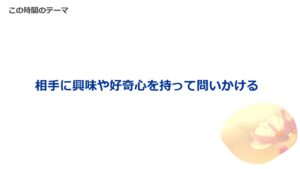
ご依頼をいただきありがとうございました。
対話をもっとおもしろく。
相内 洋輔
◆ワークショップや研修のご相談は下記から◆
どうぞお気軽にお問い合わせください。

コメント